◆「人間力」から学ぶ
前回、私は東北は宮城の山奥で生まれ、育ち、小学校しか出ていない若者が、たった一人で自力で電気を起こしてしまったというお話をしました。
今回は九州は不知火海に面した半島、女島で生まれ、中学校しか出ていない猟師の息子が水俣病と向き合い、その運動を通して思索を重ね、人として至高の境地に達するというお話です。
この二人に共通しているのは、学校の勉強はあまり好きではなかったこと、通学の途中、寄り道ばかりしては、のびのびと自然と遊び、仲間からも多くを学んだことです。また大家族の中で、愛情いっぱいに育てられたというのも似ています。兎に角、二人とも知識ではなく、知恵があるのです。人間力とでも言ったらよいのでしょうか。
◆大家族の中で育った語り手
詳しくは、本文を読んで頂くとして、少しだけ、ご案内いたしましょう。この本もまた前回と同じく、主人公の語りで構成されています。
語り手、緒方正人さんは、1953年、漁業を営む網もとの家に生まれました。20人兄弟の末っ子で、肥後もっこすの父に大変可愛がられて育ちます。石牟礼道子さんの言葉を借りると「人情もひときわ純な家系」となります。
正人さんが小学校に上がる半年前、健康そのものだった父が急に元気がなくなり、3ヶ月の闘病の後亡くなってしまいます。水俣病でした。緒方家では、その後、水俣病が次々に発症します。正人さんも例外ではありませんでした。
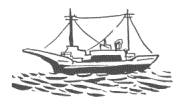
|
|
◆水俣病の運動に関わるなかで
正人さんは1974年水俣病認定申請患者協議会に入り、心身共にめいっぱい運動に打ち込んでいきました。1981年には会長に就任したのです。しかし運動に入って10年近くの月日が経つうちに、彼の中にある疑問がもち上がってきました。自分は金のためにやっているんじゃない。なぜこうまでして補償運動をやらなければならないのか、自分でもだんだんわからなくなってきたのです。
◆なんのための運動?
認定されて補償金を受ければ受けるほど、逆に患者たちも世間も水俣病について語らなくなり、問題がかえって見えなくなっていくということが、だんだんわかってきました。患者から見れば、補償金をもらってしまえば一区切りついてしまう。家の中でも外でも語らなくなる。いくら訴えてももうそれ以上の金が出てくることはないし、あんまり騒げば、今度は縁談などに悪影響が及ぶ。いよいよ水俣病が金銭的な意味しか持たなくなってきてしまったのではないか、という疑問が正人さんの中で大きくなっていきました。
◆苦しみのなかで
1985年、彼は運動から抜ける決意をし、同時に認定申請を取り下げてしまいます。申請を取り下げることを決めてから実際に取り下げに行くまでの間、彼はたった一人で考え、悩み、泣き、揚句狂ってしまいます。三ヶ月の魂の苦しみを経て彼は正気に戻ったのですが、その後の彼の行動、思考に私は強く感銘を受けました。2、3彼の言葉を引用してみます。
|

