東北の人たちのしんぼう強さと、やさしさ、それに、そこはかとなくただようユーモアに打たれました。東北人とは一体どんな人だったのかそれを知りたいという思いが強くなりました。
◆山と川が学校だった小松さんの話
「みやぎ民話の会」の代表小野和子さんから頂いた御本をめくっているうちに、飛びっ切り素晴らしいおじさんに出合いました。
小松仁三郎さんです。昭和七年、宮城県加美郡の山又山の一軒家で生まれ育ちました。小学校の分校まで、子供の足で二、三時間もかかる山奥です。
| 一家は父方、母方の祖父母、両親、兄弟八人におじを加えて十五人です。家族はひとりひとりそれぞれの持ち場を受け持って助け合って暮していました。 |
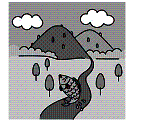 |
仁三郎さんは、学校の勉強はあまり好きではなかったようです。そのかわり好奇心は旺盛で山の猟の得意なおじつぁんと、川のことならなんでも知っている魚捕り名人のもう一人のじつぁんについて山をめぐり川にもぐって、自力で生きるすべをしっかりと身につけていった様です。「山と川がおらのほんとの学校だったね」と述懐しています。
分校で六年が終って高等科二年のとき、日本が戦争に負けて、新制中学が出来たのですが、仁三郎さんの家からは遠くて通えません。学校はやめてじいちゃんの炭焼きだの木伐りだの手伝っていました。
◆ラジオが聞きたい!
仁三郎さんは民謡が大好きで、将来は民謡歌手になりたくて習いに行ったこともあったのですが、じんつぁんに
「民謡歌手なんて、かどづ門付けして歩く乞食と同じだ。百姓のお前がそんなもの習ってなにすんだ。最後はろくな死に方しねぇからやめろ」って叱られ、唄もさっぱりうまくなんないので歌手になることはあきらめました。でも、どうしてもラジオで民謡をうたうのが聞きたくてたまりません。昭和二十五年ころになって、みんな家で電気やラジオがついてんのに、仁三郎さんの家ではまだランプでした。
小野田の町の電力会社まで頼みに行ったら、「あんだの家、山の中の一軒家ですぺ。そこに電気引くとなると、なんぼのお金かかると思ってるんだ。たった一軒家のために引いてらんねちゃや」と言われてしまう。
「くやしかったねぇ」
と仁三郎さん。
寝ても起きても、電気のことが頭からはなれなくなり、とうとう自力で電気をおこしてしまうのです。後のお話は、仁三郎さんご自身の言葉で語っていただきましょう。
◆電灯をつける
仙台の七夕見物に行った帰り、汽車の中で知り合いの東北学院の学生とたまたま隣り合わせになったのしゃ。
「こいなわけで、なんとしても電灯つけたい」つったらば、
「自動車のバッテリに電気ためて、それで電気おこせばいい」って教えられて、すぐ仙台に引き返してバッテリ買ったのしゃ。
「電球は船で使うのが効率がいいよ」って、その店の人に言われて、こんどは、石巻の船具専門の店まで買いにいった。「六ボルトの電球なら電圧低くてもつくから、バッテリ使うんならこいつのほうがいいよ」船具店でそう言われて、六ボルトの電球を買ったのしゃ。
◆水車の失敗
さあ、バッテリと電球はそろったが、肝心の動力がない。困ってしまったさ。本で調べたり、電力会社さ行ったりして、水の力利用すればいいってわかったのしゃ。
おらの家の前にはいっつも水が流れてる。水ならなんぼでもある。米搗くのに、大きな水車を使ってたから、その水車が回る力を利用することにした。
|
|
水車にダイナモとバッテリと電球をつないでみた。水を流したら、水車はカプカプってあんばいよく回るんだぉん。もっとさぶざぶ水を送ったら、ダイナモが、ウッウッーってうなりながら回った。
「しめたっ」
みんなして、そのまわりに集まって、電気今つくか今つくかって見てたけども、だめだ。ヒカッともつかねぇ。なんぼ水かけても、やっぱりだめさ。がっかりしたな。
◆工夫を重ねて発電に成功!
がっかりしてたら、黒川郡大和町吉田の嘉太神にある分校に風力発電で電気おこしてる相馬先生つう方がいるって聞いたから、さっそく行って、見せてもらったのしゃ。
さすが先生だね、えらく科学的なんだ。羽のついた鉄の輪が風を受けると、コッコッコッと回って電気がおきるのしゃ。
ところが、風力発電は、風のあるときはいいが、風が吹かないとだめなのさ。こりゃ、おらの水車のほうがよほどいいと思ったね。水さえあれば、いつでも回ってくれる。
「先生。おらのほうがいがす」つったら、こんどは、先生、川前まで見にきたのしゃ。そしておらの水車を見ると、「ここまでつくったお前の頭はたいしたもんだ。だがね、こいなのは回転数づのが大事なんだ。電気おこすには、ダイナモが一分間に千五百回は回んなくてはだめだ」つうんだ。
そう言われて、おら、水車の前にすわってじっと数えてみたさ。したら、一分間にたった二百回しか回っていなかった。千五百回にするためには、水車をもっと大きくしなくてなんない。
さあ、さっそくつぎの日、板買ってきて、でっかいのに挑戦しゃ。真っすぐな板を丸くしなわせていくのだから、まず、たいへんだ。何回も何回もつくりなおして、やっとできたときは、うれしかったね。大きな水車だよ。水かけたら、グルン、グルン回って、電気どんどんおきてきたぉんな。
相間先生を呼んできて、
「どうだ。先生」
ったら、
「うーん。よくつくったもんだ」って、えらく感心してしゃ、先生もおらの眞似して水車に切り替えたんだ。 |
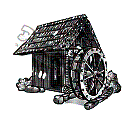 |
「できたから見にこい」
っていわれて、行ってみたさ。
さずが先生だ。おらみたいに、板に釘をダンガダンガうちつけてつくるようなことはしないのしゃ。
給料一ヶ月分使って、鍛冶屋に鉄の水車つくらせたのしゃ。だから、一定の速さで、ギィーギィーと回るわけだ。
おらのは、ガタンコ、ガタンコ回って、電灯も、ポッポ、ポッポと、へづにつくのしゃ。
そんでも、ピカッと電灯つくたびに、なんともいえずうれしかったものしゃ。
◆テレビは不思議な箱
新吉じんつぁんは相撲大好きでさ、昔、東京で見た相撲を、もう一回見たいっつのが夢だった。
おらの電気ではバッテリが弱くてだめだから、船で使うバッテリなら強いって聞いて、そいつまた買ってきて、九十になるじんつぁんに、はじめてテレビ見せてやった。 |
 |
じんつぁん、首かしげてや、
「東京でやってる相撲が、この箱に映るわけないべ。中にフィルム入って動くんだべ。フイルムがこわれたら、おしまいだべ」 って、はじめは本気にしないのしゃ。
それでも、じんつぁん、毎日、釘づけになって、テレビの相撲見ていたよ。
おらが、電気おこしたつう話が広まって、あっちからもこっちからも、
「電気おこしてくれ」
って来るようになってさ、「電気おんちゃん」なんて呼ばれて、山奥の、まだ電気が来ていない家からたのまれて、よく電気おこしに行ったもんだった。
| 川前の家に電気がきたのは、昭和四十年になってからのことだった。 |
 |
|